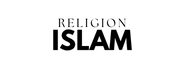親愛なる兄弟よ、
まず、コーランから一つ確認してみましょう。
1) 「彼は、二つの東と二つの西の主である。」
(ラフマーン、55/17)
(その)文言に現れる
「二つの東、二つの西」
この表現は、複数の真実を示唆しています。
「夏と冬の季節に、日照時間が長くなったり短くなったりするのに合わせて、東と西に移動する。」
という意味です。
(ザマフシャリー、IV/445; ベイダーヴィー、VI/139)
したがって、この節では季節の両極端が言及されており、その両極端の間にある毎日の東西という概念は、人々の心に委ねられているのです。
2)「東と西の主を立てて誓って!」
(マアリッチ、70/40)
この節の翻訳では、「東」と「西」という言葉が使われています。
「東と西」
このように複数形で使われていることから、太陽には複数の東と西があることが示唆されます。
地球が球状であるため、半球ごとに東と西が存在します。ある地点が東とみなされる場合、同時に西とみなされることもあり、逆に西とみなされる地点が東とみなされることもあります。
(イブン・アシュール、XXVI/247; ヤズィル、VII/370-371)
3)
クルアーンは雄弁な書物です。雄弁とは、状況に即した表現のことです。したがって、クルアーンがまずその時代の人間、つまり当時の人々に向けて語っていることは、雄弁の要請にかなっているのです。当時だけでなく、およそ14世紀の間、人々は太陽の東からの昇りと西への沈みという、目に見える東と西の概念で生活していました。しかし現在では、複数の東と西が存在することが分かっています。上記の2つの節で述べられている2つの真実が、この2つの節に示されています。
-この原則に従って、預言者ムハンマド(peace be upon him)が用いた表現には、初期の人々や各時代の一般の人々、そして近年の人々や科学者たちが理解できるような表現様式が用いられています。
それでは、預言者ムハンマド(さ)の
「太陽が沈むと、彼はアッラーの玉座の下でひれ伏して祈る。」
この言葉を、一般の人々は、朝と夕方に太陽が昇って沈むことだと理解するでしょう。しかし、科学者たちは、東と西は数多く存在し、太陽は沈むたびに天の玉座の下でひれ伏し、再び昇る許可を求めているのだと理解するでしょう。
しかしながら、今日、世界どこにいても(極地やその周辺地域を除く)、どの地域の人々も、太陽の動きに基づいて、自地域における東西の概念を認識します。そして、この認識は正しいものです。目に見えるのはそれだけです。
関連する預言の言葉は以下の通りです。
「日没の時にモスクに入ったところ、預言者(ムハンマド)が座っていた。預言者(ムハンマド)は私にこう言った。」
「アブ・ザルよ、あの太陽はどこへ行くのか、知っているか?」
と言った。私は、
「神と使徒だけが知っている。」
と私が言うと、彼はこう言った。
「彼は礼拝をするために許可を求めに行き、許可される。まるでいつか彼に」
「ここから生まれて!」
「そう言われるだろう、そして彼はまた同じ場所から生まれ出るだろう。」
そして、預言者ムハンマド(ムハンマド)は後に
「太陽は、定められた場所へと流れ去っていく。」
(ヤシーン、36:38)
という聖句を読み上げた。」
(ティルミジ、フィテン、22)
説明:
1.
このハディースは、古くから人々を悩ませてきた問題について説明しています。
「太陽は夕方にどこへ行くのでしょうか?」
現代人にとって、この質問はもはや興味深いものではありません。ここでは、預言者ムハンマド(s.a.v.)がアブ・ザル(r.a.)に質問し、答えを述べています。いくつかの伝承では、アブ・ザルが質問し、預言者ムハンマド(s.a.v.)が答えているとされています。
2.
預言者ムハンマド(ムハンマド)の回答に関する学者たちの解釈は様々です。このハディースは次のように理解できます。クルアーンは、すべての存在が崇拝していると述べている一方で、
(イスラ、17/44)
太陽に拝礼する者たちの中で、特に言及する
(ハッジ、22/18)
ある学者たちは、万物の崇拝とはどのようなものかという問いに、次のように答えています。
「それは本能的な行為であり、つまり、何のために創造されたのか、その仕事や義務を果たしたならば、それは崇拝となる。」
と彼らは言った。それゆえ、太陽は常に光を放つという義務を果たし、礼拝を行い、ひれ伏しているのである。私たちにとっての沈むとは、私たちへの光の放出という義務を放棄することではなく、世界の他の大陸で同じ義務(礼拝)を果たすために移動することである。
「アシュの下に降りる」という表現は、次のように理解できます。アシュは全ての天を包み込んでいるので、そもそもアシュの下に降りるという事態はあり得ません。昼間、私たちから見て頭上に、地平線に見える太陽が、夜に見えなくなると、それは私たちから相対的に遠く離れ、見えなくなっているという事なのです。この場合、宇宙論の知識を持たない人々に、彼らを納得させられる最も正確な答えは、これではないでしょうか。
3.
太陽が沈んだ場所から昇ることは、終末の兆候である太陽が西から東へ昇ることを示しています。太陽が西から東へ昇るという出来事を、比喩的な意味で解釈し、イスラム教がこの方法で到来すると考える人もいます。しかし、この考えは間違っているわけではありませんが、真の意味を無視することは適切ではないと考えています。なぜなら、一つの預言には複数の意味がある可能性があるからです。
太陽が西から昇る時、誰もが信じるでしょう。しかし、その時、意志と自由がもはや意味を失っているため、悔い改める門は閉ざされているでしょう。それまで信仰していなかった人々が、その日に信仰したり、礼拝に励んだとしても、その善行は受け入れられず、何の価値も持たないでしょう。
(ムスリム、イマーン、248;イブン・マージェ、フィタン、32)
なぜなら、もう時すでに遅しだからだ。
太陽が西から東へ昇る時、崇拝と試練は終わり、自由意志は失われるでしょう。それまで開かれているであろう悔い改めの扉。
(イブン・マジェ、フィテン、32)
閉ざされ、もはや悔い改めることにも何の益もないでしょう。この点に触れて、ベディウッザマンは、太陽が西から昇るときには、人間に意志と自由がなくなるだろうと述べています。
「もし試練がなければ、選択肢も存在しない。そして、この秘密と知恵のために、奇跡は稀にしか与えられない。また、試練の場において目に見えるであろう、終末の兆候や、終末の条件は、クルアーンの中の曖昧な部分のように、閉じていて解釈が必要となる。ただ、太陽が西から昇ることは、明らかにすべての人を承認に強制するため、悔い改めの門は閉ざされ、それ以上の悔い改めや信仰は受け入れられなくなる。なぜなら、アブー・バクルとアブー・ジャフルは、承認において共にいるからだ。」
(シュアルール、884頁)。
ハディースにおいて
「太陽が西から昇る」
これは、真に重要な問題として扱われ、アブ・ザル(ラ)によって伝えられた、そして上記で言及された預言者の教えにも含まれているものです。
再び彼の解釈に頼ると、ベディウッザマンは、太陽が西から昇るということを、その言葉通りの意味、つまり西から昇るという形で捉え、それは比喩を必要としないと述べています。
「ただこれだけだ」
と述べ、さらに次のように付け加えている。
「アッラーは、この太陽が西から昇る見かけ上の原因を知っておられる。地球という球体の頭脳に相当するクルアーンが、その頭から離れると、地球は狂ってしまい、アッラーの許しによって別の惑星に衝突し、東から西への運行を西から東へと逆転させる。そうすれば、太陽は西から昇り始めるのだ。そう、アッラーの堅牢な綱であるクルアーンが、地球と太陽、そして天と地を強く結びつけている力の糸を切断すれば、地球の綱が解け、無秩序に動き回り、その逆行的な動きによって太陽は西から昇る。そして、衝突の結果、神の御旨によって世界が終わるのだ…」
(Şualar, 496-497頁)
「太陽が西から昇るのと、世界が終わるのとでは、間隔はほんのわずかしかないだろう。」
この件に触れた預言の教えでは、二人が布を広げて取引しようとしたが、取引を終えて布を片付けることができず、ある男がラクダの乳を搾ったが飲むことができず、ある男が動物に水をやるために水槽を用意したが動物に水をやることはできず、ある男が口に食べ物を運ぼうとしたが食べることができずに、その時に世界が終わると伝えられています。
(ブハリー、フィタン、25;ムスナド、II、313)
しかし、これらすべてが数時間で起こるだろうと考えるべきではありません。これも他のいくつかの事項と同様に比喩的な表現であり、時間の短さを表現するためのものです。
ご挨拶と祈りを込めて…
質問で学ぶイスラム教