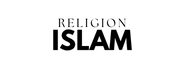-「あなたは墓の中の人々に聞かせることができない。」という経文にもかかわらず、なぜ墓の中の人々に教えや挨拶が送られるのでしょうか? – もし死者に挨拶や教えを送るという預言の言葉が真実であるならば、この経文と預言の言葉の矛盾をどのように解決できるのでしょうか?
親愛なる兄弟よ、
死後、亡者の状態については、コーランとハディースに詳細な記述があります。宇宙の唯一の創造主を知り、善行を積んだ者は、死の瞬間から高貴な地位にいるとされています。
(イリイイーン)
彼らには決して恐怖や悲しみはなく、不信者や暴君は激しい罰を受ける監獄生活を送ることになるだろう。
(シッチェン)
と述べられています。
ファラオとその一党が朝夕に火にさらされるという経文は、不信者、暴君、偽善者の死後の状態を物語っています。一方、信者たちは…
「心が待ち望み、目が喜ぶ」
つまり
物質的な感覚と精神的な感情の両方で
彼らは、神の慈悲の現れを享受する人生を送るでしょう。
死者が現世と繋がっているかどうかは、彼らの状態と関連しています。関連する伝承から分かるように、不信者は来世で自分の苦しみで忙しくなるでしょう。それどころか、預言者ムハンマドは、墓の中で苦しんでいる人々の声を聞いたと伝え、人間と精霊以外は皆その声を聞いたと述べています。
(ブハリー、葬儀編66、85;ムスリム、楽園編17;ナサーイー、葬儀編115参照)
それは、彼らに課せられた罰の厳しさを示している。そのため、彼らは人々と接触できる状態にはないだろう。一方、信者たちは肉体的にも精神的にも進化していくだろう。
墓地が拡張され、照明が設置され、楽園の庭園の一つとして整備される予定です。
そのため、彼らは世界との連絡を維持できるでしょう。
このようにして
「霊的な賜物」
(挨拶、朗読された経文から得られる功徳)
彼らに向かっていくと、彼らの霊的な恵みが私たちにも届くのです。」
(言葉、第29の言葉、698ページ)
神のために殺された者たちを、決して死者とみなしてはならない。彼らは生きており、主の許で糧を得ているのだ。
(アル・イムラーン3:169)節と
「信者たちよ、そしてイスラム教徒の地の住民たちよ、あなたたちに平和あれ」
(ムスリム、葬儀、104;イブン・マージャ、葬儀、36)という預言者の言葉は、信者の来世における生活のこの側面を強調している。
「生きている者と死んでいる者は同じではない。確かにアッラーは、ご自身の望む者に聞かせる。だが、お前は墓の中の人々に聞かせることはできないのだ!」
(ファティル35:22)の節は、不信者の状態を述べています。この世で不信の闇の中にあり、真理に耳を閉ざし、洞察力を失っているように、来世でも苦しみに囚われ、何かを聞いたり関心を持ったりする余地はないでしょう。
死者が墓に埋葬され、埋葬の手続きが完了した後、死者に訓戒をすべきかどうかについて、学者たちの間には異なる意見があります。死者は墓に埋葬されると、もはや現世の人々の声を聞くことが不可能であると主張する者たち(1)は、訓戒は死者にとって何の益にもならず、与えるべきではないと述べています。一方、墓の中の死者は生者を聴くことができるが、生者は死者の声を聞くことはできないと主張する者たちは、訓戒を与えることができると述べており、預言者ムハンマド(s.a.w.)がベドルの戦いでアブ・カシブ族に語りかけたことを、死者が神が望めば生者の声を聞くことができるという証拠として挙げています(2)。
イマーム・アブー・ハニーファは、
彼は、勧告は義務付けられても禁止されてもいないものであり、人々は葬儀後に勧告を行うか行わないかを自由に選択できると述べた(3)。
イマーム・シャーフィイーは
埋葬後の勧告は推奨されると述べています。イマーム・アフマド・イブン・ハンバルもシャフィイーと同じ見解です。勧告を推奨するシャフィイー派は、墓に埋められた者が、去っていく親族の足音を聞く(4)ことや、預言者ムハンマドが بدرの戦いで殺された多神教徒に呼びかけた(5)という預言の言葉を根拠としています。
イマーム・マーリク
「亡くなった方々にも、ラ・イラーハ・イッラッラフを唱えさせてあげなさい。」
(6)
のハディースにおいて
「死者」
から
「臨終の患者」
彼は、それが意図されたことであると述べ、埋葬後の教え込みに関する信頼できる情報がないため、死者に教え込むことは忌むべきことであると述べている。(7)
霊魂に語りかけるべきかどうかは議論の余地があるが、墓の中の者が自分に語りかけられているのを聞くという伝承がある。
ベドルの戦いで、戦いの終結後、クレイシュ族の戦死者は井戸に詰め込まれた。そこで、アッラーの使徒は彼らにこう語りかけた。
「ああ、〇〇の子〇〇よ、〇〇の子〇〇よ!汝らは、アッラーとアッラーの使徒が汝らに約束したことを、真実だと見いだしたのか?私は、アッラーが私に約束したことを、真実だと見いだしたのだ。」
と述べた。ウマル・イブン・アル=ハッターブは言った:
「アッラーの使徒よ!あなたは、魂のない死者にどのように語りかけるのですか?」
と尋ねると、預言者(ムハンマド)はこう言った。
「私が言ったことを、あなた方は彼らよりもよく聞くことはできないでしょう。ただ、彼らは答えることができないだけです。」
(ムスリム、楽園、76、77)
と仰った。
預言者ムハンマドが墓のそばを通りかかったとき、そばにいた人々にこう言った。
「信者の故郷の住人たちよ、平安あれ!」
と仰って、挨拶するように命じられました。
(ムスリム、葬儀篇、102;アブー・ダーウード、葬儀篇、79;ナサーイー、清浄篇、109;イブン・マージェ、葬儀篇、36、禁欲篇、36;ムワッター、清浄篇、28)
挨拶は挨拶に応える者に返されるべきであるから、死者は自分を訪れる者を認識しているということになる。精緻な学者として知られるイブン・カイイム・アル=ジャウズィーヤも、死者は特に金曜日と土曜日に訪れて祈る者や、子供たちの良い行いを聞いて喜びを感じていると伝えている。(イブン・カイイム・アル=ジャウズィーヤ、『クルフ論』、10)
ファティル(35)章の、墓にいる者たちは聞かないという経文は、前の経文と合わせて解釈されると、ここで不信者が死者に例えられていると解釈されます。
「盲者と視覚を持つ者、闇と光、日陰と暑さは同じではない。生きている者と死んでいる者も同じではない。確かに、アッラーはご自身の望む者にのみ聞かせる。お前は、墓の中にいる者たちに聞かせることはできない。」
(ファティル、35/19-22)
この節を前の節と合わせて考察すると、通説によれば、この比較例において肯定的なものは真理、信仰、信仰者、そして彼らが得られるであろう幸福を、否定的なものは虚偽、否定主義、否定主義者、そして彼らが受けるであろう不幸を表している。この点に関する解釈は、以下のように要約できる。
信者の歩む道は堅実であり、視野と洞察力は開けており、意志と決意は堅く、彼らの行いは永続的で有益である。一方、不信者は死者と変わらず、洞察力は閉ざされ、心は暗く、彼らの行いは意味を帯びず、無駄に終わる。
(8)
ラージー
これらの例には、次のような説明が当てはまります。
「目撃者」
という言葉は信者を意味します。
「盲目」
「カフィリ」という言葉は、
「明るさ」
信仰、
「暗闇」
異教徒の
「影」
快適さと安らぎ
「暑い」
苦痛と燃えるような熱を
「生きている者たち」
信者たち
「死者」
これは不信者を説明するために使われています(9)。つまり、彼らは聞いたことを理解できず、受け入れられないという点で、墓の中の者たちと同じ状態にあるということです。
ここで、不信者の状態は、魂のない死体のように何も感じたり聞いたりしない状態であり、墓の中の死体が人間を聞き取れないように、不信者たちは不信の闇のために、預言者よ、あなたの言葉を聞き取れないという意味で理解できます。
霊界にいる魂は墓と関係があるため、挨拶や呼びかけは肉体ではなく魂に対して行われると理解されています。
脚注:
1. 死者は生者の声を聞けないと主張する者は、証拠として「(や رسول)あなたは(この دعوت)を死者に伝えることはできない…」(ルム、30/52)という経文と「…あなたは墓にいる者たちに聞かせることはできない。」(ファティル、35/22)という経文を挙げ、また、預言者ムハンマド(S)が بدرの戦いで戦死者たちに語りかけたことを、弟子たちへの説教や忠告として解釈する。(el-Hapruti, Abdullâtif, Tekmile-i Tenkihu’l-Kelâm, s. 145, İst.)
2. el-Harputi, 145-146, イスタンブール 1332; Ibnü’l-Hümâm, I, 446-447.
3. イスラム法学四宗派論、I、501頁。ジェズィーリ著。ベイルート、1972年。
4. ブハリー、葬儀、68; ムスリム、楽園、70-72.
5. ブハリー、メガーズィ、8; ムスリム、楽園、76-77.
6. ムスリム、サヒフ、葬儀篇、第2巻、631頁。
7. 7. el-Ceziri, el-Fıkhu Ale’l-Mezâhibil-Erba’a, I, p. 501. ベイルート, 1972.
8. タベリ、注釈、第22巻、128-129頁。
9. ラージー、『タフシール』、XXVI、16。
ご挨拶と祈りを込めて…
質問で学ぶイスラム教