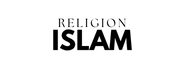親愛なる兄弟よ、
遺言では、子供や親族への最後の訓诫を述べなければなりません。権利を持つ者たちとの和解、債権・債務の精算、借金の返済、遺産の分割、もしあれば巡礼の借金の代理人派遣などを求めるべきです。葬儀や埋葬後の希望も伝えるべきです。妻への未払いの婚約金(Mehr-i müeccel)の支払いを遺言で指示しなければなりません。これらの希望が実行されるように、公正な二人の証人の前で遺言執行者を選任しなければなりません。
遺言は宗教的な観点から5つのグループに分類されます。
a. 義務遺言:
生前に支払うべきであったが支払えなかった借金、あるいは他者に対する権利(これらの借金は神に対する義務である場合もあれば、人に対する義務である場合もある)を、遺言によって支払う、あるいは権利者に渡すように遺言することは、イスラム教徒にとって義務である。したがって、他人の預かり物を持っている者、あるいは借金があり、その借金の存在を証明する証拠がない者は、預かり物を権利者に渡すこと、借金を支払うことを遺言しなければならない。同様に、巡礼、施し、断食などの義務を負っているが果たせない者、あるいは償罪の義務を負っている者は、巡礼と施しを果たすこと、断食の償いを渡すこと、償罪を支払うことを遺言しなければならない。(1)
b. 望ましい遺言:
裕福な人が、相続人ではない親族、貧しい人々、そして慈善団体に遺言を残すことは推奨される。
c. 許容される遺言:
親族や見知らぬ人であっても、裕福な人に対して遺言を残すことは許されています。
d. 忌避される遺言:
貧しい相続人がいる場合、その人が自分の財産を他の人に遺言することは、全会一致で忌まわしいとされています。さらに、ハネフィー派の意見では、誰であっても、悪徳な者に遺言することは、厳しく忌まわしいとされています。
e. 遺言として許されないもの:
違法な行為を目的とした遺言は、全会一致で違法です。例えば、イスラム教徒が教会建設やワイン醸造所建設といった違法なものを遺言することは違法です。このような遺言は履行されません。
また、たとえ正当な目的であっても、遺産の3分の1を超える遺言は認められません。
遺言がなされている場合、相続人は遺産の3分の1を超える部分については、その遺言に従う義務はありません。ただし、従うことも可能です。ハンバリ派の正統な見解によれば、このような遺言は忌避すべきものです。(2)
出典:
(1) 参照:イブン・クダーマ、『アル=ムグニー』、VI、444;イブン・アビディン、『レッドゥル=ムフタル』、VI、648;ワフバ・ズハイリー、『イスラム法とその根拠』、VIII、12。
(2) 参照:イブン・クダーマ、前掲書、VI/445; ズハイリー、前掲書、VIII/12, 13.
ごあいさつと祈りを込めて…
質問で学ぶイスラム教