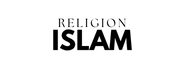– ある質問への回答として:
「女性は、結婚時に離婚権が自分にも与えられることを条件に、結婚に同意することができます。この権利は、生涯にわたるものもあれば、一定期間だけのものもあります。」
お疲れ様でした。
– このような状況で、女性に与えられる離婚料はいくらですか?
– つまり、離婚の際に妻に渡されるのは離婚金のうちどれくらいですか?全額渡されますか?
親愛なる兄弟よ、
イスラム法によれば、離婚権は男性に属し、男性は自ら行使することも、代理人を通じて行使することもできます。この代理人は誰でも構いませんが、妻であることも可能です。離婚権を第三者に委任することを委任と呼び、第三者を代理人といいます。
しかし、もしその人が離婚権限を自ら配偶者に与えたのであれば、それは権限を与えることになります。
「離婚委任」
奥さんにも
「ムファヴァザ」
と言います。
1
付け加えておくべきことは、この方法で夫から離婚する女性は稀であるということです。女性がイスラム教が彼女たちに与えた権利を知らないこと、そしてそのような要求をする女性が歓迎されないことの両方が、テフヴィズ・イ・タラク制度を理論上のものにとどめているのです。
テフヴィズ・イ・タラクの定義:
単語
委任
ある仕事の管理と運営を他の人に委任し、任せることです。
また、テフヴィズ・イ・タラクとは、
イスラム法において、
「夫が持つ離婚権限を妻に委譲し、離婚を妻の意思と希望に委ねること。」
と表現されています。
これはこの委任状とは異なる処分であり、夫はこれを撤回する権利を持たない。
2
代理離婚の種類:
委任は、時間制限の有無によって3つの種類に分けられます。3
1. 徹底的な委任:
一度の離婚に限定されない委任です。夫から妻への
「私はあなたに離婚する権利を与えました。」
(離婚しろ)と言うようなものだ。
2. 有期委任:
一定期間、夫が妻に離婚する権利を与えることです。
「私が遠征に行った時に、あなたに自分を離婚する権利を与えたのよ。」
まるでそう言っているかのようだった。
3. 一般委任:
時間的な制限を設けずに、夫が妻に離婚権を与えることです。
「私はあなたに、いつでも自由に離婚する権利を与えました。」
まるでそう言っているかのようだった。
代理離婚の合法性について:
テフヴィズ(代理履行)の正当性は、コーランとハディースによって確立されています。コーランには:
「預言者よ、あなたの妻たちにこう言いなさい。『もしあなたがたがこの世の生活とその飾りを望むなら』」
(幸福を)
もしあなたが望むなら、離婚の慰謝料を支払って、あなたたちを美しく解放してあげましょう。もしあなたが神の使徒と来世を望むなら、神はあなたたちのうちで美しく振る舞う者たちに、大きな報いを用意しておられることを知ってください。」
4
と述べられています。学者たちの大多数によれば、女性が世俗的な生活を選ぶという意味は、離婚を要求することです。したがって、離婚権は彼女たちに与えられたのです。5
また、アブー・ハーン(ラ)も:
「預言者ムハンマド(さっららっと)は私たちを自由にしてくれました。私たちは神と使徒を選びました…」
6
と述べています。この記述から、彼らには離婚を希望した場合、離婚する権利があったことがわかります。7
代理離婚の時期:
離婚権限の女性への委譲は、結婚契約から
まず
予定通り、結婚式
即座に
またはそれ以上
その後
でもできます。
ハネフィー派の教義によれば、男性は結婚契約を結ぶ前に
「もし私たちが結婚したら、いつでも離婚できるわよ。」
このようにして女性に離婚権を与えることで、女性は離婚権を持つことになります。ハネフィー派がこの見解を持つのは、離婚が結婚前に可能であることを認めており、タラク(離婚)を結婚の条件にすることを認めていることの結果です。8
離婚権限の譲渡に関する委任、委託、譲渡という用語の違いについて:
夫が妻に離婚権限を与えること
代理離婚
と述べました。委任はいくつかの言葉で表現されます。例えば、
「自分の欲望を抑制せよ」、「問題は自分次第だ」、「望むなら自分を解放せよ」
9. これらの言葉を用いることで、夫は妻に離婚権を与える際に、時には自分の名において行使させることを意図し(委任)、時には離婚権を完全に妻の裁量に委ねることを意図する。
(譲渡)
意図する。いくつかの宗派では、委任と譲渡は同じものとみなされるが、他の宗派では、異なる結果をもたらすため、同じものではないとみなされる。10
夫が妻に離婚権限を委任した場合、夫はもはやその発言を取り消すことはできませんが、委任者は代理人をいつでも解任することができます。もし委任が一定期間に限定されている場合、その期間が過ぎると妻の権利は自動的に失われます。代理離婚権限を与えられた者は、解任された後はその権利を失います。11
離婚権限を女性に
委任、委託
または
譲渡
このように表現されることは、非常に重要な問題ではなく、区別できないほど複雑な言葉や表現で実行されるため、混乱を招く可能性があります。そのため
「ことはあなたの手に委ねられている。自分の欲望を克服しなさい。望むなら、自分を無に帰しなさい。」
特定の言葉を使うことは、特にアラブ以外の社会にとっては必須ではなく、本人が望む言語や言葉でその権限を与えることは可能です。そのため、アラビア語を話せない人々は、タヒールとマシイアの違いを知ることはできず、妻に代理人を任命したい場合や、離婚権を完全に与えたい場合に、どの言葉を使うべきかを知ることはできません。したがって重要なのは、配偶者が、自分が住む社会で理解されている言葉を使って離婚権を与えることです。
代理離婚の効力:
離婚権を持つ女性がその権利を行使して夫と離婚した場合、それは不可逆的な離婚(バイン・タラク)となり、女性の同意がない限り、男性はたとえ委任、譲渡、代理の意図があったとしても、婚姻関係に戻ることはできません。12
もし離婚権限が時間的に限定されて与えられた場合、その期間が満了すると、女性の離婚権は失効します。例えば、男性が「明日、あなたは自由に選択できる。離婚するか、しないかはあなた次第だ」と言った場合、女性がその日中に離婚しなければ、離婚権を失うことになります。13
テフヴィズ・タラク(委任離婚)を受けた女性が、この権利に基づいて夫と離婚する場合、何回分のタラク(離婚)が有効となるかについて、意見が分かれています。一部の意見では、1回分のタラクのみが有効となる一方、夫がこの権限を付与する際に、女性が何回分のタラクを使用できるかを明示していた場合は、その回数まで離婚できるという意見もあります。
イスラム教が女性に与えたこの権利は、
個人の自主性に委ねられているため、適切に活用されていません。女性の多くは、そのような権利があることを知らず、権利を知っていても、非難されたり悪意があると非難されたりすることを恐れて、権利を主張することができません。女性がイスラム教が与えたこの権限を行使すれば、多くの不当な扱いから解放されるでしょう。
脚注:
1. ムハンマド・ムヒッディン著、『イスラム法における個人に関する事項』、メクトベトゥル・イルミエ、ベイルート、2003年、300頁。
2. Ömer Nasuhi, Hukuk-i İslamiyye ve Istılah-ı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen Yayınları, İstanbul, 1985, (I-VIII), .II /.177; İbn Rüşd, Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed el-Hafid el-Kurtubi, Bidayetü’l-Müctehid ve’n-Nihayü’l-Muktesid, Daru’l-İbn Hazm, 1995, II / 41.
3. アブデュルハミット、前掲書、304-305頁;ビルメン、前掲書、II /177.
4. アハザーブ、33/28-29。
5. クルトゥービー、ムハンマド・ブン・アフマド・ブン・アビー・バクル、『アハクーム・アル・クルアーン』、ベイルート、1985年、XIV / 170.
6. ブハリー、タラーク、5、第6巻、165頁;ムスリム、タラーク、4、第2巻、1104頁;アブ・ダウード、タラーク、12、第2巻/653-654頁。
7. ドンドゥレン・ハムディ著、『証拠を伴う家庭教理』、アルティンルク出版、イスタンブール、1995年、418-419頁。
8. イブン・アビーディーン、ムハンマド・アミーン、『レドゥル・ムフター・アレッ・ドゥルリ・ル・ムフター』(アブドゥル・アズィーズ・アブドゥル・ラフマーン・アッラーム訳)、シャミル出版、イスタンブール、1983年、VI/349; ズハイル、ワハベ、『イスラム法百科事典』(翻訳委員会訳)、リサーレ出版、イスタンブール、1994年、IX/334.
9. チン、ハリル、『旧法における離婚』(第2版)、セルチュク大学出版、コンヤ、1988年;『イスラム法とオスマン法における婚姻』、アンカラ大学法学部出版、アンカラ、1974年、68頁。
10. イブン・ルシュド, 前掲書, III / 41; ドンドゥレン, 前掲書, 138頁.
11. アブドゥルハミット、前掲書、301頁。ベクル、『クルアーンの判例』、ベイルート、1985年、XIV/170。
12. チン、前掲書、69頁;ドンドゥレン、前掲書、418頁。
13. アブデュルハミット、前掲書、304頁。
ごあいさつと祈りを込めて…
質問で学ぶイスラム教