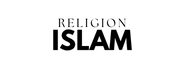別れの説教における言葉:
「神はすべての権利を持つ者にその権利を与え、相続人に相続分を割り当てた。遺言書は必要ない。」
2章(アル・バカラ)180節:
「あなたがたの誰かが死に近づいたとき、もし遺産を残すならば、両親と近親者に対して、正当な方法で遺言を残すことは、敬虔な者たちにとって義務とされた。」
– この2つの記述は明らかに矛盾しています。非常に信頼できるハディースである別離説教が、コーランと矛盾しているのはなぜでしょうか?
親愛なる兄弟よ、
「あなたがたの誰かが死に臨んだとき、もし遺産を残すならば、両親、近親者に対して、慣習にかなった遺言を立てることは義務とされた。これは敬虔な者たちに対する権利である。」
(2:180)
2章(アル・バカラ)のこの節で
-死の兆候や前兆が現れたため、まもなく死ぬだろうと考える人々-
両親や親族に遺言をすることを命じられています。この遺言の命令が義務なのか、推奨事項なのか(またはスンナなのか)については、二つの異なる見解があります。
この二つの見解のうち、より正しいとされる見解によれば、遺言は義務であった。遺産に関する啓示が下されたことで、この啓示は廃止され、神によって定められた相続分が決定された。それ以降、権利の所有者は、遺言者の恩恵に頼ることなく、直接的に相続人となった。
(イブン・カシールによる、該当する経文の注釈)
イスラム教以前のアラブ社会では、相続は次のように行われていました。亡くなった人の
男の子たち
もし息子がいたら、彼らは全遺産を受け継ぐでしょう。息子がいない人の財産は、近親者から遠親者へと順に相続されます。
男性の親戚に
そうした財産は、遺言によって子供、親戚、友人などに相続されることもあった。
この聖句は、まず第一に両親を指し、男女の区別なく、
すべての親族に遺言を残す必要がある。
彼は、後に来る相続の規定に備えて、信者たちにそのことを伝えました。ニサー(女性)章の相続に関する経文(4/11など)では、すでに相続分を受け取っているこれらの男性を直接言及せずに、
女性の親族も相続人に含めました。
(参照:ラーイー、該当する経文の注釈)
この節を無効にした規定が何かについては、意見が分かれています。2つの解釈は以下の通りです。
まず第一に:
この節の効力を廃止する
ニサー(女性)章の11-12節は、相続法を定めたものです。
第二に:
この節の規定を廃止したものは、質問にも挙げられている
「実に、アッラーはすべての権利を持つ者にその権利を与えた。もはや相続人への遺言はない。」
という意味のハディースです。
(参照:ラージー、イブン・カシール、該当する経文の注釈)
言い換えれば、初めて遺言の効力を無効にしたのは、
遺言に関する節です。
別れの説教で言及された預言者の言葉には、
この廃止の決定は、改めて確固たるものとなりました。
この問題となっている預言者の教えが、遺言に関する規定を直接的に廃止したと考えるにしても、あるいは廃止的な遺産相続に関する規定を裏付ける立場にあると考えるにしても、いずれの場合も
-質問で言及されている-
この預言と、問題となっている遺言に関する経文との間には、矛盾はないことは明らかです。
なぜなら、一方はお互いを無効にするものだからです。
しかしながら、ダッハーク、タウース、タベリーといった法学者によれば、遺言に関する経文は相続に関する経文とは別に存在し、つまり何らかの理由で
(宗教が異なる両親、奴隷である親戚など)
遺産相続の権利がない親族が、遺言によって遺産の一部を受け取ることを
を目標としています。
誰にどれだけの遺言がされるかは、慣習、習慣、そして公平の原則(慣例的な基準)に委ねられています。
「近親者が、同じグループに属する遠縁の親族を相続から除外すること」
(ハジブ)の原則により相続人となることができない孫(祖父の孤児)の問題は、現代のいくつかのイスラム諸国では、このイフティハド(法解釈)を利用することで解決され、孤児の孫が遺産を相続できるようになっています。
例えば、父親が祖父よりも先に亡くなった子供は、祖父の保護下に置かれた孤児です。やがて祖父も亡くなると、子供の叔父が祖父(つまり、亡くなった祖父の生きている息子、父親)に祖父よりも近い関係にあるため、相続を受け、孫は相続から除外されます。子供が亡くなった父親の代わりに(後継者として)相続人となるという規定はイスラム法にはありません。このような場合や同様のケースでは、
「相続人となり得ない近親者」
問題が生じます。これらに対して必要な(義務的な)遺言の規定も、この問題の解決に用いられます。
また、遺言は、実際に実行されることが死後に委ねられた法的行為です。
ある人が生前に権利や義務を負っていた場合、その権利や義務を遺産から支払ったり、履行したりするための遺言を残すことは義務です。そのような義務や権利の所有者への返済が不要な場合は、遺言は義務ではなく推奨事項であり、状況が許せば行うべき推奨される法的行為であり、宗教的な奉仕と崇拝です。遺言を推奨する預言者の言葉は、このように解釈されています。
(ブハリー、遺言、1;ムスリム、遺言、1, 4)
ごあいさつと祈りを込めて…
質問で学ぶイスラム教