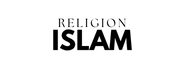-タウバ(悔悟)章12節において、マウドゥーディーの注釈では、誓いを破る者たちを背教者であると主張している。この主張は10節と11節に結び付けられており、悔悟し礼拝する多神教徒が誓いを破る、つまり背教者となるならば、と述べている。
– しかし、他の学者たちは、ここで誓いを破ったのは多神教徒であり、背教者ではないと言っています。どちらの解釈が正しいのでしょうか?
– タウバ(悔悟)とは、12人の多神教徒のことですか、それとも背教者のことですか?
親愛なる兄弟よ、
タウバ(悔悟)章7-16節:
「アッラーに異神を伴侶とする者たちに、アッラーと使徒との間に、いかなる契約がありうるだろうか?ただし、聖地メッカの近くで、彼らと契約を結んだ者たちは別である。」
彼らがあなたたちに対して正直であれば、あなたたちも彼らに対して正直な態度を示しなさい。なぜなら、アッラーは自分を恐れる者たちを愛されるからである。」(7)「彼らに約束などあるはずがない。もし彼らがあなたたちに勝てば、親族の絆も、約束の義務も守らないだろう。彼らは口ではあなたたちを喜ばせようとするが、心の中ではそれに反対している。彼らの多くは不義な者たちである。」(8)
「彼らは、わずかな報酬と引き換えにアッラーのしるしを売り渡した。そして人々をアッラーの道から引き離した。彼らがしていることは、実に悪いことである!」(9)
「彼らは、信者に対して親族関係も、契約の義務も守らない。まさに彼らは、暴虐を働く者たちである。」(10)
「しかし、もし彼らが悔い改めて礼拝を行い、施しを施すならば、彼らはまさにあなたの兄弟たちである。知識のある民に対して、我々はこうして節々を詳しく説明する。」(11)
「もし彼らが契約を破り、誓いを破って、あなたの宗教を冒涜するならば、不信仰の首謀者たちと戦いなさい。彼らは誓いを守らない者たちである。そうすれば、彼らはきっと諦めるであろう。」(12)
「彼らは誓いを破り、預言者を故郷から追放しようとし、しかも最初にあなたたちに侵略を始めたのです。そんな民と戦わないのですか?」
それとも、彼らを恐れているのか?しかし、神は、
-もしあなたが真の信者であるなら-
「彼こそ、あなたが恐れるに値する者である。」(13)「彼らと戦いなさい。そうすれば、アッラーは彼らを汝らの手によって罰し、彼らを恥辱に陥れ、汝らに彼らに対する勝利を与え、信者の群れの心を安らげ、彼らの胸に宿る怒りを鎮めるであろう。アッラーは、ご自身の望む者の悔悟を受け入れる。アッラーは、真に知る者であり、賢明なる者である。」(14-15)
「それとも、あなたがたは、アッラーのために戦い、アッラーと、その使者と、信者以外の者を相談相手としない者たちを、アッラーが区別せずに見過ごされるとでも思われたのか?アッラーは、あなたがたの行いをよくご存知である。」
(16)
聖句の解説:
この一連の経文では、主にイスラム教とイスラム教徒に対する憎悪と敵意を、いかなる価値観も無視して満たそうとする多神教徒の態度と行動が描写されており、信者たちは、自分たちと戦争状態にあるこれらの敵に対して戦うよう励まされています。しかし、これらの経文に多神教徒に関する厳しい表現や辛辣な口調が含まれていることを、理由もなく戦争を始めたり、単に信仰のせいで他人を攻撃したりすることを正当化していると解釈することはできません。
これらの経文で重点的に述べられているのは、多神教徒の信仰や宗教生活ではなく、彼らの非人道的な行為、イスラム教徒が正当な立場にあり、信仰の闘争が勝利に終わるためには断固たる姿勢を示す必要があるということです。
7節では、偶像崇拝者との条約において、神と使徒が当事者となることはできず、そのような条約は、
–規則の範囲内で–
信者が一方の当事者となりうることを述べています。次に、盟約を破らず、イスラム教徒に不利なように他者を支援しない者たちについては、条約期間を遵守すべきであることを、原則および一般的な理解の仕方として述べる4節の降示の理由について説明し、メッカの神殿の近くで条約を結んだ多神教徒についても、この原則が適用されることを思い出させています。
(エルマリーリ、IV、2462)。
メッカのイスラム教寺院(マスジド・アル・ハラーム)の近くで条約を結んだ人々が誰であったかについては、様々な意見がある。
(タベリ、第10巻、81-82頁)
イブン・イスハークによる以下の伝承は、歴史的知見に照らしてより強力かつ正確であると見なされています。フダイビヤ条約に間接的に関与したキンーナ族ベニ・ベキル部族の一部は、他の部族とは異なり、この条約を遵守したのです。
ここに経文があります。
「禁廟の隣に」
これは、メッカ周辺で締結されたフダイビヤ条約、および間接的にこの条約の当事者となり、その条項を破らなかった集団を指している。
(タベリ、X、82-83)。
ここで注目すべき点は、政治的および道徳的な根拠が失われ、本来的当事者に対して条約の解除が通知された場合でも、間接的に当事者である者が条約の規定に違反しない限り、彼らに与えられた約束は守られるべきであるということです。
この経文では、この範囲に属する人々が約束を守る限り、彼らに与えられた約束も守られると述べられています。このコーランの考え方は、高い法的原則を含んでおり、イスラム法学者もこの理解に基づいて国際関係の枠組みの中で次のような規則を開発しました。
「疑いこそが、真の信頼である。」
(エルマリー、第4巻、2463-2464頁)。
この規定は、保証が与えられた可能性があれば、保証が与えられたものとして扱われるべきであることを述べています。この節で、間接的にこの条約に関与した人々が意図されているという解釈を採用した場合、ヒジュラ暦6年に締結されたフダイビヤ条約が10年間有効であったことを考慮すると、彼らにさらに7年間の猶予を与えるべきであるという結論に至ります。
8~10節では、信者たちは、対峙する多神教徒たちの性質について警告され、彼らが些細な利益のために神のしるしを売ったり、預けられたものを裏切ったりしたことを思い出させられ、彼らが窮地に陥った時に発する言葉や、やむを得ない状況や自分の利益のために結んだ契約を、あまり信用しないように求められています。
11節では、他の節の表現や文体から、多神教徒への道は完全に閉ざされ、彼らは永遠の敵として見なされるべきだと信じることを避けるために、信者たちに特別な注意喚起がなされていることが理解されます。なぜなら、これらの否定的な特性にもかかわらず、多神教徒が良識を養い、自分のしたことを悔やみ、イスラム教の基本的な義務を果たし始めれば、イスラム教徒の兄弟姉妹として扱われると述べられているからです。
「不信仰の首謀者たち」と訳される12節の表現は、不信仰において最も先頭に立っていた多神教徒全体を指している可能性もあれば、イスラム教徒への敵意と迫害を主導した多神教徒を指している可能性もあります。コーラン全体の文脈は、この両方の解釈を許容するものです。
(Derveze, XII, 86-87)。
誓いを破る者たちと戦うよう信者を励ます13節が誰を対象としているかについての伝承は、主に2つのグループに分類できます。
いくつかの伝承によれば、ここで言及されているのは、フダイビヤ条約を破ったクレイシュ族のことである。他の伝承によれば、ここで言及されているのは、条約を破ったために、この章の冒頭で破棄通知が伝えられ、4ヶ月の猶予を与えられた者たちである。この一連の節が、メッカ征服後に降示されたと知られる前の節の続きのように見えること、そしてクレイシュ族の全族または大部分がメッカ征服後にイスラム教に改宗したことを考慮すると、この節でクレイシュ族について言及されているという伝承を説明するのは困難である。
ここで、クレイシュ族以外の集団が意図されていると考えるならば、別の疑問が生じます。この節では、これらの人々が預言者ムハンマドを故郷から追放したと述べられていることから、彼らがクレイシュ族以外である可能性はありますか?この場合、次のような解釈が適切かもしれません。クレイシュの同盟者であり、間接的にフダイビヤ条約の当事者であったバヌー・バキル部族のいくつかの派閥。
–上記のとおり–
条約の条項を遵守した者もいれば、クレイシュの扇動によって条約を破った者もいました。ここで言及されているのは、メッカ征服後も裏切りと誓約違反を続け、この章の冒頭の通告の対象となった集団である可能性が高いです。彼らは、預言者ムハンマドを故郷から追放したクレイシュの人々と同一陣営にいたため、そして彼らが最初に条約を破ったため、このように記述されているのでしょう。
この解釈の続きとして、14節で信者の勝利を喜ぶと述べられているのは、フザーア族の人々であると言えるでしょう。なぜなら、彼らはフダイビヤ条約に、預言者ムハンマドの同盟者として間接的に関与していたからです。そして、クレイシュはフザーアの敵であるバヌー・バキルを支援していました。
(Derveze, XII, 88-89)。
これらの節の冒頭にある戦争に参入した理由に関する説明と合わせて、12、14、15節の記述を考慮し、戦争で何を達成しようとしたのかにも注意を払うべきです。
これらの経文から分かるように、戦争の目的は、血に飢えた者たちがそうするように、単に相手を傷つけ、破壊し、拷問することではありません。むしろ、12番目の経文の最後に、常に希望を抱いて戦うべきであり、戦争で何を期待すべきかが、優雅な言葉で表現されています。それによると、目的は、約束を守らない敵を威嚇することであり、この制裁によって敵が侵略的な行動をやめるという希望を抱いて進めていくということです。
この意味に関連して、14節では、罰と恥辱に値する敵は実際には神によって罰せられること、信者はこれを自己中心的な問題として扱わず、神の命令を実行する手段として自らを認識すべきであることが示されています。言い換えれば、信者は自己の欲望や利益の流動に身を任せず、常に自らの行動の正当性の根拠を熟考するように求められているのです。
また、14節と15節では、勝利を与え、心に安らぎを与え、心の恨みや怒りを鎮め、望む者の悔い改めを受け入れるのは常にアッラーであると繰り返し述べられており、したがって、信者はこの信念を保ちながら行動を調整すべきであると求められています。
神の試練を受けるために創造された人間にとって、神からの召しに応えて不正義と戦い、それを宗教が定める枠組みの中で行うことができることは、この試練の重要な一部である。
16節では、信者が人間的な尺度から見ても大きな献身と呼べるような努力を、この試練の過程の当然の延長線上にあるもの、そして義務として捉えるべきであり、いつでもそのような呼びかけに応えられるように精神的に準備しておくべきであると述べられています。
(参照:ディヤネト・テフシル(トルコ宗教局の注釈)、クルアーン・ヨル(クルアーンの道)、関連する経文の注釈)
ごあいさつと祈りを込めて…
質問で学ぶイスラム教