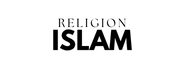– ズマール39/10とバカラー2/97の節に注目すると、「言え」という言葉は必要ないのですが、使われています。
親愛なる兄弟よ、
関連する経文の訳は以下の通りです。
1.「言え、もし誰かが جبرائيل(ジブリール)を敵とみなすなら、彼は知っておくべきだ。このクルアーンは、以前の書を裏付けるものとして、信じる者たちにとっての導きと福音として、アッラーの許可によって、彼(ジブリール)があなたの心に降ろしたのだ。」
(2:97)
この節では、一般的に知られている表現の形に従って(訳語として)
「言わなさい。『…それは、アッラーの許可によって、私の心に啓示されたものである』」
という表現の代わりに、
「言わなさい……それは、アッラーの許しによって、あなたの心に降ろされたものです。」
という表現が好まれるようになりました。
– まず、アラブ人社会に限らず、他の人々の中でもこのような表現は広く使われています。例えば、
– 誰かに:
「あの男に言ってくれ、『私を大切にしてくれ』と」
という表現の代わりに、
「…君を大切にしてね」
と言えるでしょう。むしろ、もっと毛が生えてくるかもしれません。
– フェルダドゥックという有名なアラブの詩人は、ある詩の中で、要約すると以下の言葉を述べています。
「ある日、私は通りすがりの場所で泣いていたんです。ヒンドゥー語で:
「私に何が起きているの!」
と呼びかけた。」(イブン・アティヤの該当する経文の注釈を参照)。
実際、この表現は一般的に知られている、より一般的な形としては:
「…どうしたんだ、と声をかけたんだ」
こうあるべきだった。
2. 「(私から彼らに)こう伝えなさい。信じる僕たちよ、汝の主を畏れなさい。この世で善行をなす者は、必ず善報を得るであろう。アッラーの国は広大であり、真理の道に忍耐した者には、無限の報酬が与えられるであろう。」
(ズマー、39/10)
この節の難しさは(訳文として)
「言え、信じる僕たちよ!」
という表現です。ここでは、一見すると、使徒たちが預言者ムハンマドに帰属しているように見えます。この点については、次のように説明できます。
a.
上記の聖句の訳文に括弧で囲まれた表現が含まれている場合があります。これは物語の語り口が用いられていることを意味します。
「(私から伝えなさい)言え、信じる僕たちよ!」
b.
「わが僕たちよ」
というように訳される、呼びかけ/呼び出しの文体には、暗黙のうちに次のようなものが含まれている。
「割り当て済み」
が意味する意味が問題となります。この場合、
「言わなさい。『ああ、信じる僕たちよ!』」
文の意味
「言え、信じる僕たちに…」
という形になります。
(参照:クルトゥビー、シャウカーニー、該当する経文の注釈)
– この節の表現と似たものが、ズマール(煙)章53節にも見られます。
「言わなさい。『ああ、罪を犯し、自分自身に害を及ぼしてきた僕たちよ、アッラーの慈悲を絶望しないでください。アッラーはすべての罪を許されるからです。彼は実に、寛大で慈悲深いお方です。』」
この節の文言の説明は、前の節の説明と同様です。
これらの聖句において
「と言いなさい。」
の意訳
「クゥル」
この言葉が使われたことには多くの意味が考えられます。その中でも最も重要なのは、ムハンマド(平和と祝福あれ)が単なる使者であったことを示すことです。もしそうでなければ、ムハンマドのような最も賢く、最も流暢で、最も雄弁な人物が、このような場所で…
「奴隷」
という言葉は使わなかった。
いや、むしろイフラス(真言)の章に書かれているように
「クルフワッラフ=言わく、アッラーフは唯一無二である」
彼の発言にも
「と言いなさい。」
その表現は使わないだろう。
つまり、このような表現がコーランに掲載されているのは、
クルアーンが最初から最後まで神の言葉であることを証明するために
向けです。
しかしながら、このような表現がアラビア語で使えたことの最大の証拠は、あらゆることに異議を唱えたアラブの多神教徒たちが、コーランに書かれたこのような表現が間違っていると異議を唱えなかったことである。
ごあいさつと祈りを込めて…
質問で学ぶイスラム教