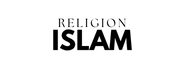– 財産を求める者、そして(恥ずかしさから)求めることができない者たちにも、権利がある。(ザリヤート、51/19)
– どのようにしてその権利が与えられるのか、詳細に説明していただけますか?
親愛なる兄弟よ、
該当する経文の意訳は以下の通りです。
「彼らは、援助を求める者や貧しい人々に、自分の財産の一定の割合を分け与えていた。」
(ザリヤート51:19)
この経文では、クルアーンはアッラーへの崇拝、アッラーへの敬意に加えて、
彼らが創造したものに対しても慈悲を示すべきだという、彼のたゆまぬ主張の
その一例として、称賛に値する信者たちが、神の偉大さを決して忘れることなく、神に許しを請うという特徴が挙げられます。
彼らの親切さ
言及されています。
所有権は神に属する。
神が創造物に与えたものは、すべて預けられたものに過ぎない。
神は、ある者々に財産や富、そして恵みを与え、ある意味で彼らを裕福にします。そして、神は彼らに、その財産や富、恵みのほんの一部を、困窮している人々に与えるように望みます。
会社や国の会計係が、与えられた資金、物資、資源を適切な場所に分配する責任を負うように、裕福な人々もまた、神の財産を神の僕たちに与え、彼らの権利を守る責任を負うのです。
つまり、
助けを求める者や貧しい人々にこの権利を与えているのは、万物すべての所有者であり主であるアッラーです。
神は、ある者たちを地位、財産、富といった恵みによって試す一方で、それらから奪うことによって試すこともある。
要約すると、
試練は両者にとってのものであり、どちらがより厳しく困難な試練であるかは分かりません。人は自分の立場や状況に応じて、自分が試練の中にいることを認識し、その試練を乗り越えるために必要なことを学び、実践しなければなりません。
「助けを求めている」
そして
「貧しい」
と訳した
「sâil」と「mahrum」
これらの言葉の意味については、様々な解釈がなされてきた。
一般的な見解によれば
「サイル」
必要性を明確に示し、さらには援助を求める。
「奪われた」「剥奪された」
一方、困窮しているにもかかわらず、頼むことをためらい、恥ずかしさや自尊心がその気持ちを表明することを妨げている人を指します。
最初の言葉で人間を、そして二つ目の言葉で他の生命体(生き物)を。
意図された意味とは異なる解釈もあり、それは人間だけでなく他の生物、特に動物の権利に注目している点で興味深いものです。
(他の解釈については、ラージー、シャウカーニーによる当該節の注釈を参照のこと)
ここで、信者たちに、メディナ時代に定められる財政的義務の規定に備えさせるための自主的な拠出金が求められていますが、財政的に余裕のある人々が、この援助を自分たちの恩恵だと見なさないように、援助は困窮している人々に支払われるべきものとして扱われるべきです。
「権利」
であることを示す表現が使われています。
むしろ、一部の学者たちは、ここでもザカートの義務を果たす人々が称賛されていると考えています。
しかし、このコメントには
「ザカート」
「ザカート」という言葉は、その基準額、割合、そして支出先が宗教的に定められた財政的義務という意味で使われていません。なぜなら、この意味でのザカートはメディナ時代に義務付けられたからです。
一方、メディナ時代に決められたザカートに関する金額は、通常の場合に適用されるものと解釈される。
「富裕層、つまり余剰財産を持つ者は、貧困層がその財産に権利を持つことを認めるべきだ」
また、これらの経文は、飢饉、危機、災害などの非常事態においては、単に決められた額のザカートを支払うだけでは、個人を責任から免除することはできないことを示していることに注意すべきです。
金持ちや裕福な人、あるいは恵まれた立場の人々にとってはそうですが、経文にあるように。
乞食と貧民
該当する人の状況について:
クルアーンと同様に、ハディースでも、名誉を保つ貧しい人々、そして貧困を悪用し、物乞いを生計手段とする人々との間の倫理的な違いに注目されています。
預言者ムハンマド(さっらллаху・アレイヒ・ワ・サルラム)
「貧しい」
(貧しい人)
1、2個のナツメヤシや数口の食べ物で済ませられるような貧しい人ではありません。本当の貧しい人は、自立した生活を送る人です。
(禁欲的な)
誰でも構いません。よろしければ、
「彼らは人にしつこく物事をねだらない。」
この節を読んでください。
(ムスリム、ザカート、102)
と述べることで、物乞いはイスラム倫理における主要な美徳である経済的自立の概念と矛盾することが明らかになった。
また:
– 自分の手で稼いで生活できるのに、物乞いをする者、特にそうやって財を蓄えようとする者は、実は地獄の火を求めているのだ。
(ムスリム、ザカート、105)
– 彼らは、この世で恥も外聞もなく物乞いをするが、来世では顔の皮をむしられた状態で神の前に現れるだろうと述べている
(ブハリー、ザカート、52;ムスリム、ザカート、103、104)。
預言者の教えは、物乞いの行為が来世においてどのような重い罰に遭うかを示している。
コーランや預言者の言葉において、他者からの援助を求めることが、名誉を傷つける行為であり、来世での罰に値する行為として示されていることは、預言者の弟子たちに深い影響を与えました。
実際、
「彼らのうち誰かの鞭が地面に落ちても、誰にもその鞭を渡してくれとは言わないだろう。」
この意味を持つ伝承は、サハバ(預言者ムハンマドの同時代者)が物乞いに対して抱いていた感受性を表現するために、様々な文献や異なる表現で伝えられています。
(例えば、ムスリム、ザカート108;アブー・ダーウード、ザカート、27を参照)
歴史を通して、どの国にも富裕層と貧困層が存在してきました。クルアーンとスンナの精神にかなう行動とは、国内の貧困層を特定し、その必要性を国家の社会福祉機関が満たすことです。もし国家にそのような機関がない場合、あるいはそれらが不十分な場合は、富裕層が貧困層の必要性を満たすべきです。
イスラム教の学者によれば、人が働けなくなるほど弱り、何らかの形で必要最低限の生活が保障されていない場合、物乞い(物乞い)は許される。
したがって、イスラム教において物乞いは生計手段ではなく、必要不可欠な場合に限って許される行為です。
です。
イスラム学者たちは、この許可を与えるにあたって、以下の条件を求めてきました。
1. 他人に手を差し伸べられる人は、本当に困窮している人でなければならない。
このような状況にある人は、しばらく待つことで必要を満たすことができる場合、そしてそれによって深刻な損害を受けない場合は、待つことを選択し、物乞いをすべきではありません。
物乞いを許容するほどの窮状の有無は、時代や地域によって異なる経済状況によって変わってきます。例えば、1日分の
(朝晩)
食べ物を所有しているイスラム教徒は物乞いをする権利がないと強調されています。したがって、固定収入のある者は給料や賃金を受け取れるまで、商業や職人技に従事する者は財政的な余裕ができるまで、借金などによって最低限の生活費を確保できない場合に限り、物乞いをすることができます。
物乞いは、必要としている人の緊急の状況に比例し、それに限定されるべきです。緊急の状況がなくなったら、他人から物乞いをやめるべきです。
2. 援助を求める人は、自尊心を保たなければならない。
彼は、適切な裕福な人に自分の必要性を伝えるだけで十分であり、彼から何かを明確に求めるべきではありません。もし求める必要に迫られたとしても、しつこく求めるべきではなく、自分を屈辱的な立場に置くような行動を避けるべきです。
3. 助けを求める相手を選ぶ際には、慎重に判断する必要があります。
助けを求める貧しい者の気持ちを理解し、自分の財産には貧しい者にも権利があることを認識し、物乞いを叱責せず、施しを自慢しない人。
(参照:2:264)
また、謙虚で、笑顔が絶えず、寛容な人物であることが望ましいです。
学者たちは、進んで与えようとしない者から施しを受けることを正当とはみなさなかった。
そして、このようにして奪われたものは、可能であれば同じものを、そうでなければその代価を返すべきだと述べています。
詳細はこちらをクリックしてください:
– 裕福な人々を不快にさせるであろう経文は、鳥に変えられてしまった。一体どうして…
ごあいさつと祈りを込めて…
質問で学ぶイスラム教